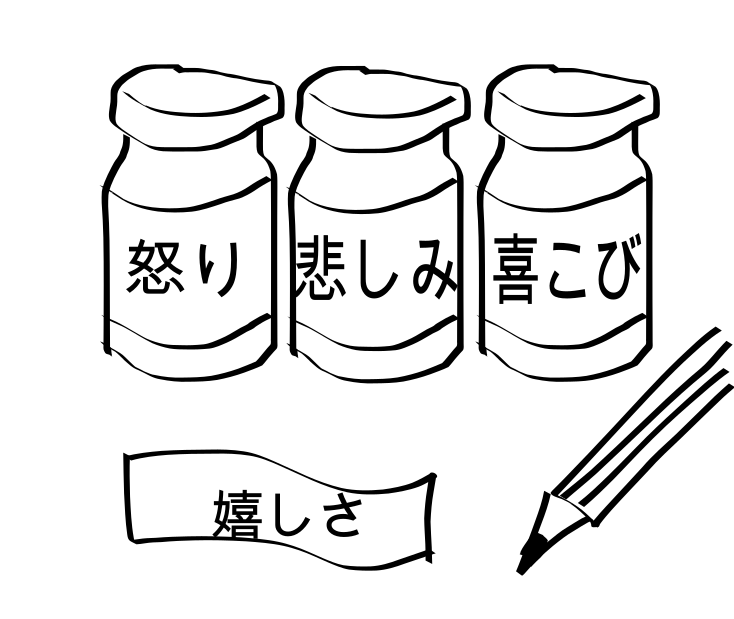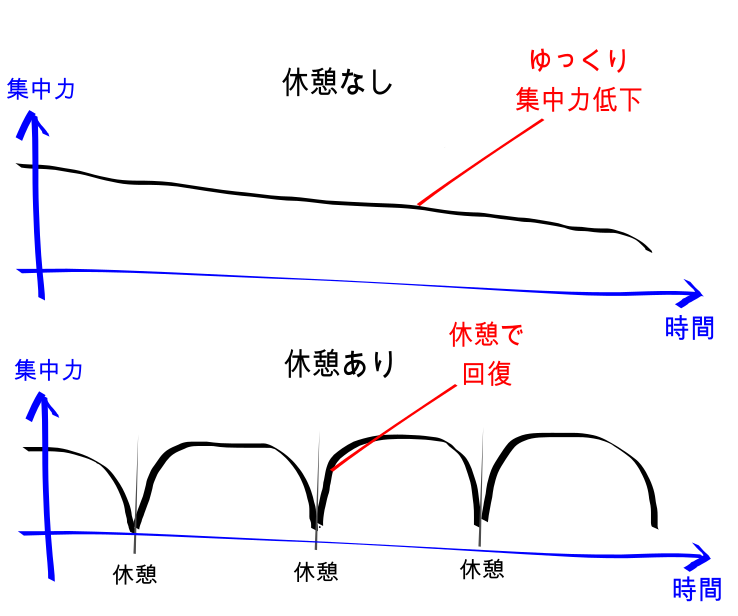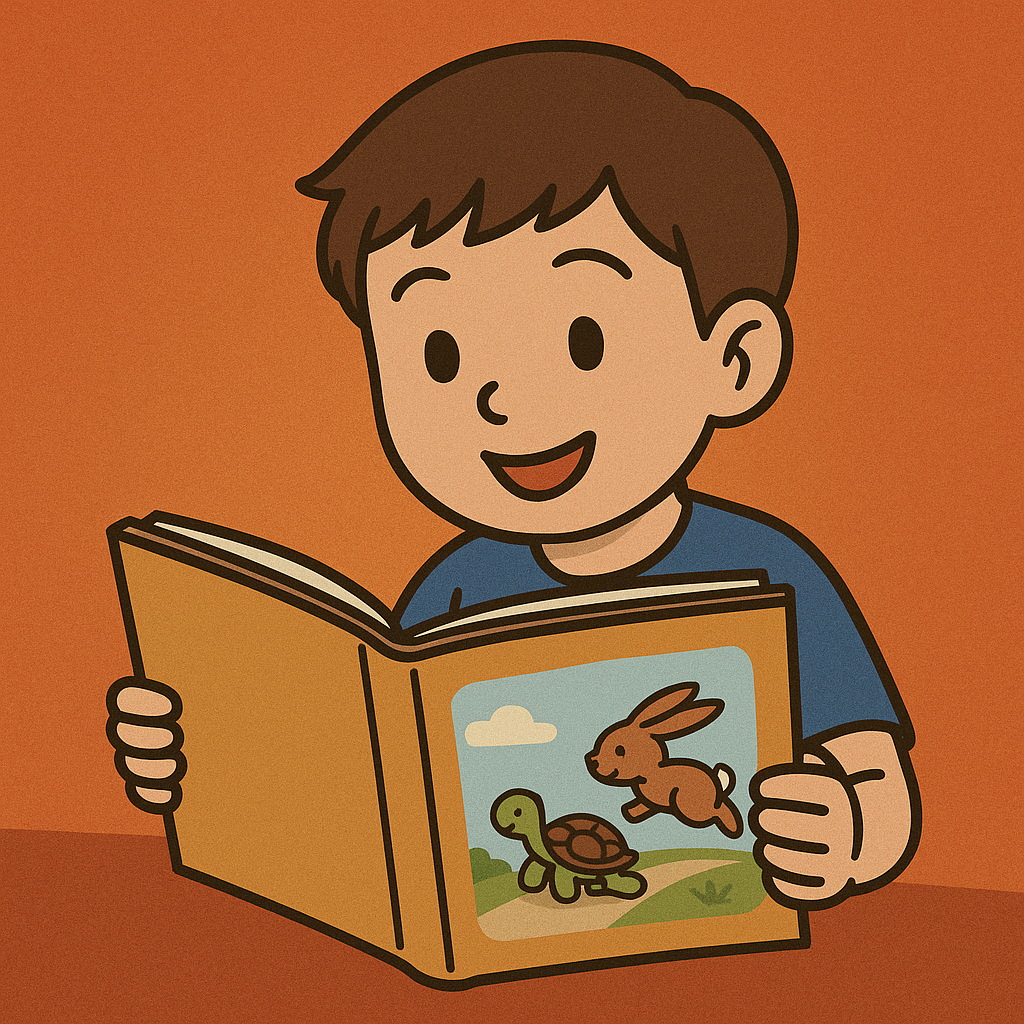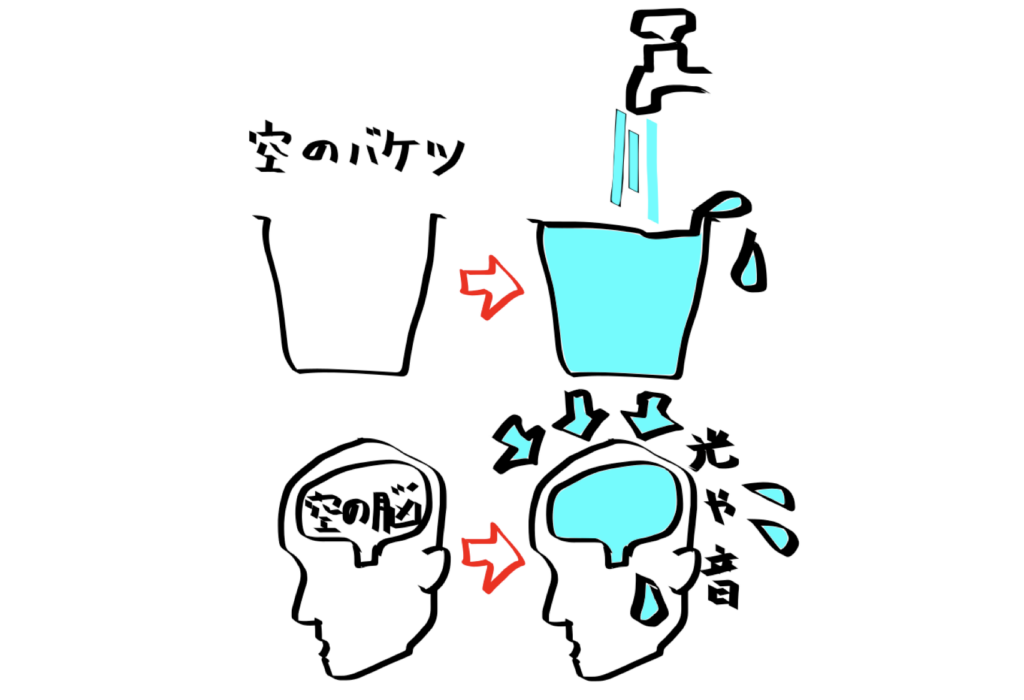緊張するのは、「受け身な状態」
になっていることが多いです。
ちゃんとゴールや目的
があれば、緊張しにくいんですね〜
具体的な目標がある状態がよい
これは逆を言えば、
やることがないと不穏になりやすい
ってことです。
なぜ目標が必要なのか?
じゃあなんで目標(ゴール)🚩とか目的🎯があると
緊張しにくくなるのか?
という話をしていきますね!
※※これ発達の理解でめちゃくちゃ⚠️重要⚠️です・・・
【目標がないと色々できる状態になる】
目標やら目的やらがない状態だと、
言ってみりゃ、
宙ぶらりんな状態になります。

『あれもできるしこれもできる』
わけです。
「たこ焼きも食べれるし、
公園に行っても良いし、
宿題をやっちゃってもいい」
みたいな。
フリーダムですね。
これはややこしい言い方で言うと
“擬似的なマルチタスク状態”
または、
“優先順位を決める必要性に迫られる状態”
・どれからやるのか?
・何をやるべきなのか?
・自分は今何をしたいのか?
フリーダムだと、
こういったことを考える必要が出てきます。
結果、「フリーズ」や「パニック」が起こりやすくなります。
でも、、
目標や目的が与えられたらどうでしょう?
『一つの目標を設定する』
↓↓↓
強制的な”シングルタスク”状態
となり、
ややこしいことを考える必要がなくなりますよね?

これは実際の支援現場でもとてもよくあります。
実際の例を見ていきましょう。
例)
継続B型事業所の休憩時間に不穏な行動を
繰り返す利用者Aさん
Aさんは休憩時間に
暴れたり、
ガラスを割ったりしてしまっていた。

[原因]
お茶飲んでも良いし、
外の空気を吸いに行っても良いし、
机に伏せて寝ても良い
.oO(何して良いかわからず、不安🫨)
[問題へのアプローチ]
明確に
“すること”
を設定することにした。
具体的には
『ジグソーパズルをしてもらう』
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
[結果]
パズルを完成させるという目標が定まる
.oO(目の前のゴールに集中できて安心😮💨)
暴れたり、ガラスを割ることがなくなった!💡
このように目標や目的、やることなど
が具体的に設定されると
発達障害の人は安心することができ、
問題行動が減ります。
※健常者だと、
「パズルをするよりこの時間で帰りに
買うものリスト作った方が良いかも…」
とか色々と考えちゃうので有効ではありません
→「発達障害と俯瞰」の項目でまた取り上げたいと思います。
・・・
というような特性が、発達障害の人にはあります。
実は、
緊張するのもこれに似ています。
例えば「雑談で緊張する」と言う場合…
雑談ってテーマが【ほぼ無限】にあります
何を話しても良いと上の例のように、
不安になります。
でも相手とどういう関係になりたいか?
どんな話がしたいか?
など具体的な目標やテーマが定まっていれば
緊張しません。
例:
『エレベーターで仲がそんなに良くない同僚と乗り合わせた』

何を話しても良い
というか話すか?話さないか?から
自分の自由。
しかもこの人と仲良くなりたいとか、飲みに行きたいとか、関係性についての具体的なゴールもない。
→緊張🫨
『誰でも良いから昨日の阪神対巨人戦の盛り上がったシーンをシェアしあいたい(あの打順と配球は奇跡だよね!という気持ちを確認し合いたい)』
→緊張せず話せる😄
とういうような感じです。
大事なのは「目的や目標が明確かどうか」なのです。
雑談は、そもそも目的がふわっとして
(一応「コミュニケーションを取ることで親密さを増す」
的な目的はあると思いますが)
いるために、発達障害の人は緊張状態になりやすいと言えるでしょう。
まとめ
今回は発達障害と緊張のメカニズムについて
お話ししました。
発達障害の人は、
雑談でなくても、明確な役割や目的がない場面では
緊張状態になりやすいです。
受け身にならず、何が目的意識や目標設定をしてみることで
緊張状態が緩和されます。
ゲームのようにルールを作って楽しんでみても良いでしょう。
ぜひ試してみてくださいね。
「なぜ緊張するのかよくわかった!」
など感想もぜひコメントしてくださいね。

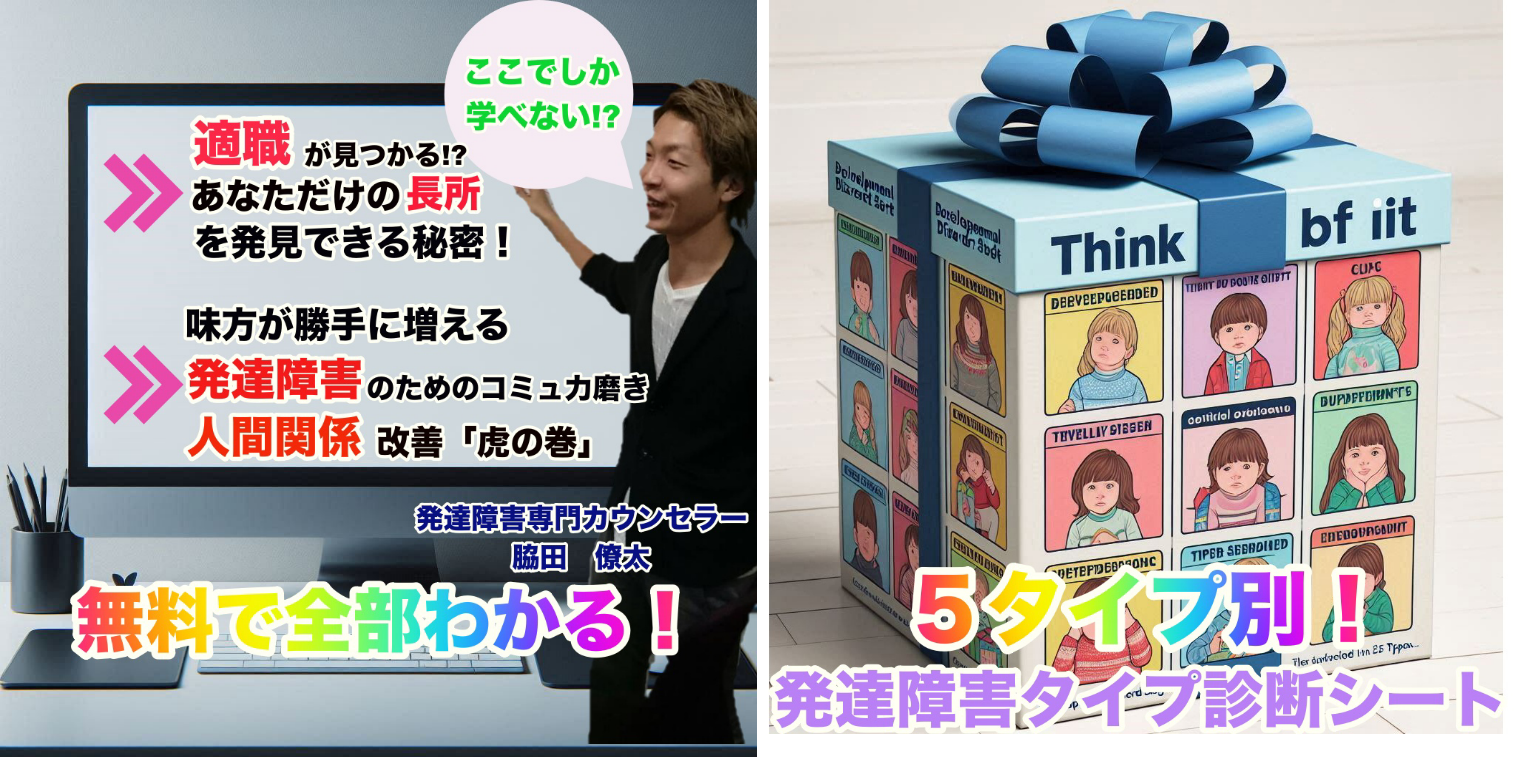 現在、友達追加特典として発達障害の中でも5タイプに分類し、自分の得意不得意がわかる
現在、友達追加特典として発達障害の中でも5タイプに分類し、自分の得意不得意がわかる