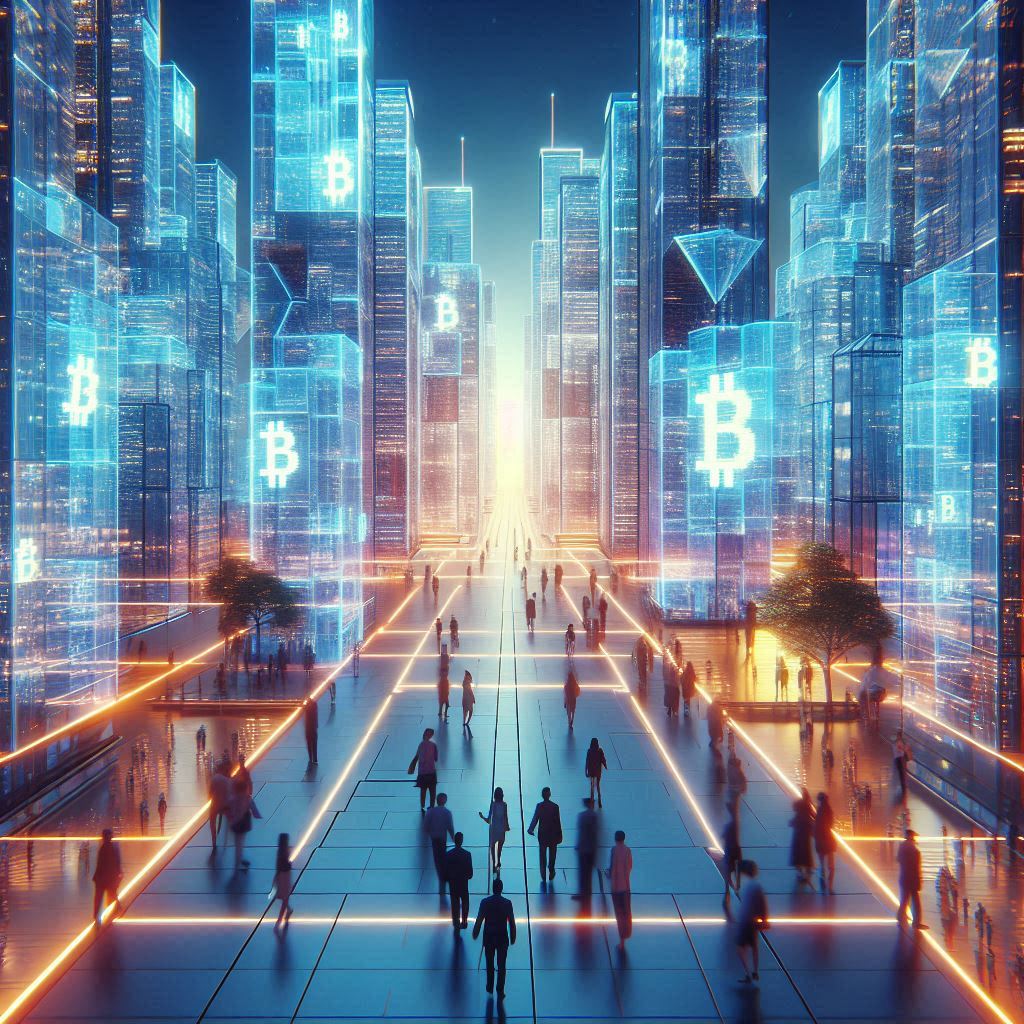↑音声で聞く場合はこちらからどうぞ。
どうも、脇田です。
今日は発達障害の人と努力について話していきたいなと思います。
財務省解体デモに関するほりえもんの発言、
『お前らは努力してないからダメなんだ』というものに対して、
炎上しているのを見ました。
発達障害の人たちは努力しすぎてしまう?
努力が大事なのは間違い無いと思います。
努力せずに成果が手に入ることはないでしょう。
しかし、努力してもうまく行かなかった経験は誰しもあると思います。
早起き、ランニング、ダイエット、勉強、語学学習など、
努力したのに成果が出ずに辞めてしまった経験は多いのではないでしょうか。
努力ができない、あるいは努力しすぎるパターンもあります。
120%の力で始め、その後徐々にモチベーションが下がり
三日坊主になる人もいるでしょう。
三日坊主を避けようと1週間頑張るものの、
1ヶ月後には別のことを始めたり、
早起きとダイエットを同時に行おうとして息切れし、
さらに断捨離も始めようとして結局全てやめてしまう、
ということもあると思います。
発達障害でも努力が報われる方法とは?
努力を確実な方法でやっていく必要があるのです。
努力してないのではなく、努力の仕方が悪いのです。
そこで、サポーター、コーチ、トレーナーといった存在が必要になります。
適切な指導があれば、努力を成果に結び付けることができるのです。
しかし、問題となるのは、トレーナーの指示を理解できないことです。
理解できないまま、
相手に「合ってますか?」と質問することをためらってしまいます。
「自分だけが分かってないのではないか」
という遠慮があるためです。
この遠慮を克服し、質問できるようになれば、
発達障害の人は他人のアドバイスを聞けるようになります。
パーソナルトレーナーを付けたり、
正しい方法を学んでから始めることが可能になるんです。
努力してないのではなく、努力の仕方が悪いのです。
師匠の言うことが理解できないけど
自信が持てず質問できない、
↓
教えを授かることができない(師匠がいない)
↓
正しい努力の方法がわからず自分流になる
これが問題だったのです。
今日の音声は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。

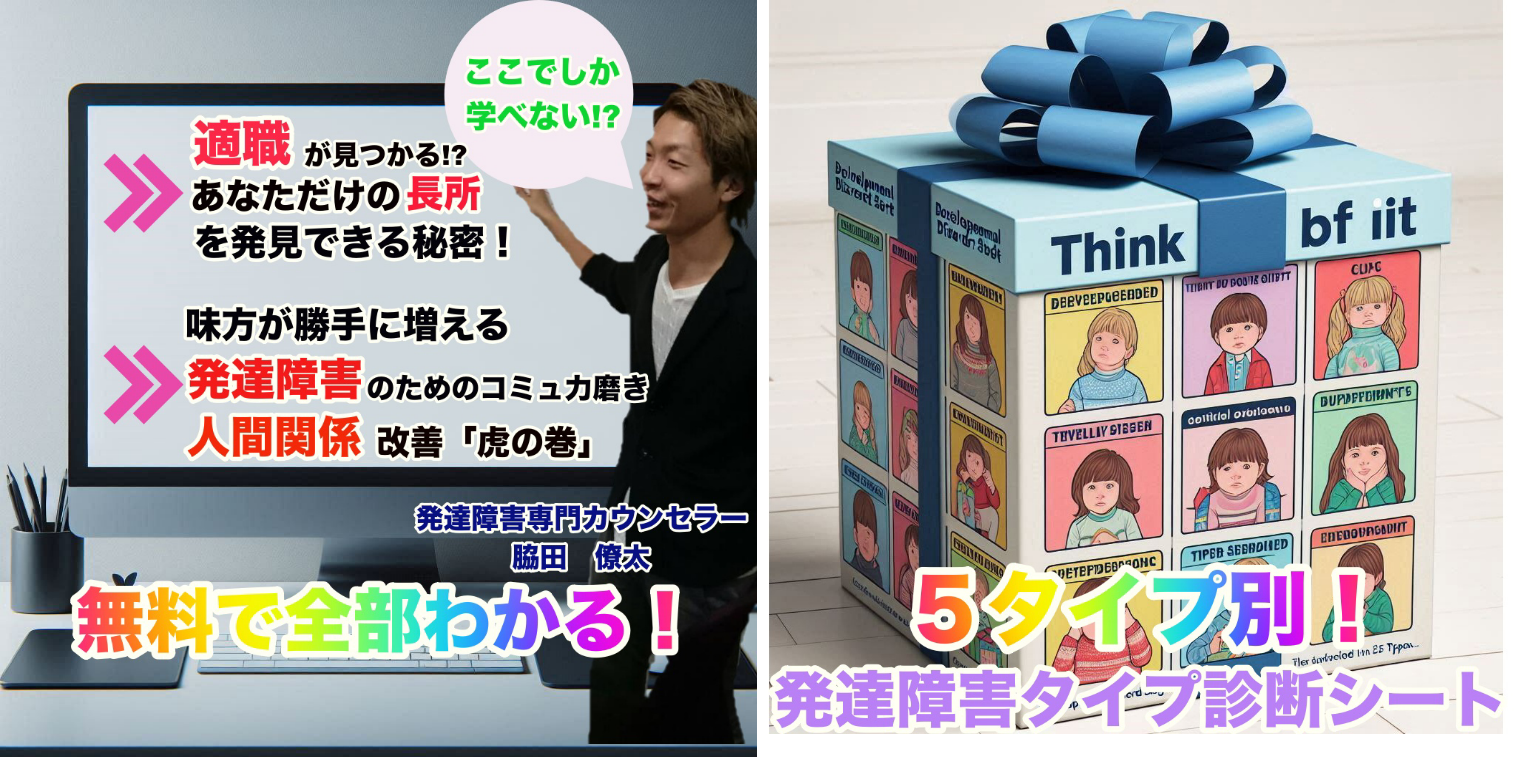 現在、友達追加特典として発達障害の中でも5タイプに分類し、自分の得意不得意がわかる
現在、友達追加特典として発達障害の中でも5タイプに分類し、自分の得意不得意がわかる