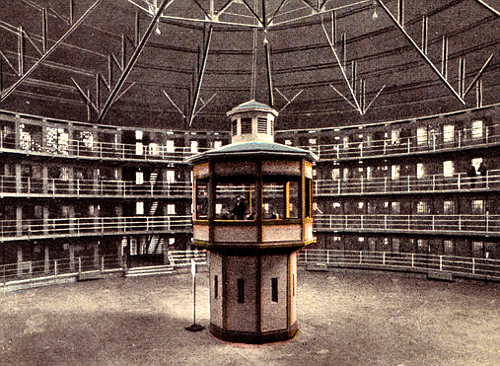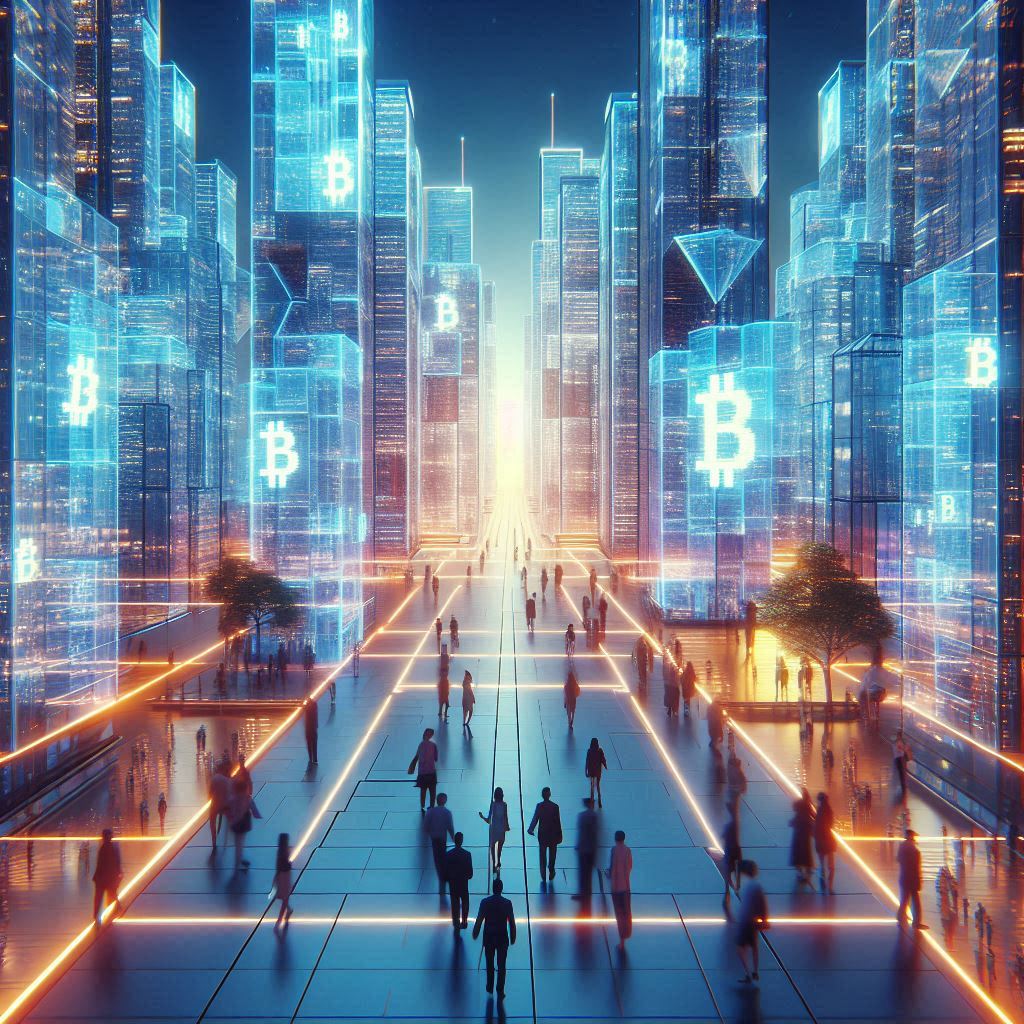↑↑↑音声で聞きたい時はこちらからどうぞ。
はい。最近ですね、HSSとかHSPっていうのが出てきてると思うんですけども、これらはですね、繊細だけど刺激を求めるタイプの人とか、普通に繊細な、センシティブなパーソン、HSPですね。
HSSっていうのが最近になって、前はHSPだけだったと思うんですけど、出て来たんですよね。このHSSっていうのが、どう見てもですね、発達障害の専門家である私からするとADHDなんですよね。
なので、センシティブパーソンHSPの方も、私から見たら受け身型ASD(受け身型アスペルガー)なんですけども、ASDやADHDっていうのがですね、まだ世間それほど浸透してない ので、おそらくですね、HSP、HSSっていうところと重なって来るんじゃないかな。
全部が全部、それに一括りは出来ないんですけども、そもそも発達障害っていうのがですね、グレーゾーンも含まれてるというか、スペクトラム性、レベル0の人からレベル10の人まで、障害の度合いというか特性の強さが変わってくるようなものなので、ここからが発達障害、ここからASDです、ここからADHDですとかいうものではないので、どっちかっていうと軽症者よりの人たちが、障害とまではいかないけれども、HSSっぽいなとかHSPっぽいな、どう見てもその、何でしょうね、受け身型っていう人たちはですね、自分の主張が出来ないとかですね、人に頼み事が出来ない、この前も書きましたけど、拒否することが出来ないとかそういう特性を持ってるっていう部分でですね、HSPの人とめっちゃ近いですし。
刺激を求めるんだけど疲れやすいっていうのはおそらくですけどADHDの特性、刺激を求める、多動性ですよね。
自分の中でその、色々なメカニズムはすごい深いんですけど、要は情報処理の障害が発達障害なんですけど、それの中で、多動性っていうのはですね、刺激を求めることでいわば自分を安定させるというか、覚醒度とかを上げて、情報の入力っていうのを、自分の中で何とかこう正常に保ちたいみたいな体の機能の一部っていうのが、刺激を求めたり依存性を高めたり、多動性があったりとかですね、不注意があったりっていうところで、自分の注意であったりとかですね、色んなものをコントロール、制御下に置けないっていう障害ですね。
それがHSSっていう概念を私が初めて聞いた時にすごい似てるなと、かなり、これは言い過ぎかもしれないですけど、同じちゃうっていう感じで、同じじゃないかっていう風にちょっと思ったんで、それはちょっと記事にしておいた方がいいのかなと。
発達障害知ってる人で、そのHSS、HSPを知ってる人がいたらまたね、何かどう思いますかっていうか、そうちゃう??っていうのはちょっと聞いてみたいんですけどね。
ていうので今ちょっと音声入力アプリで、ブログとしてまとめたいなと思ったので、ちょっと撮ってみました。以上です。
最後までお聞きいただきありがとうございました。

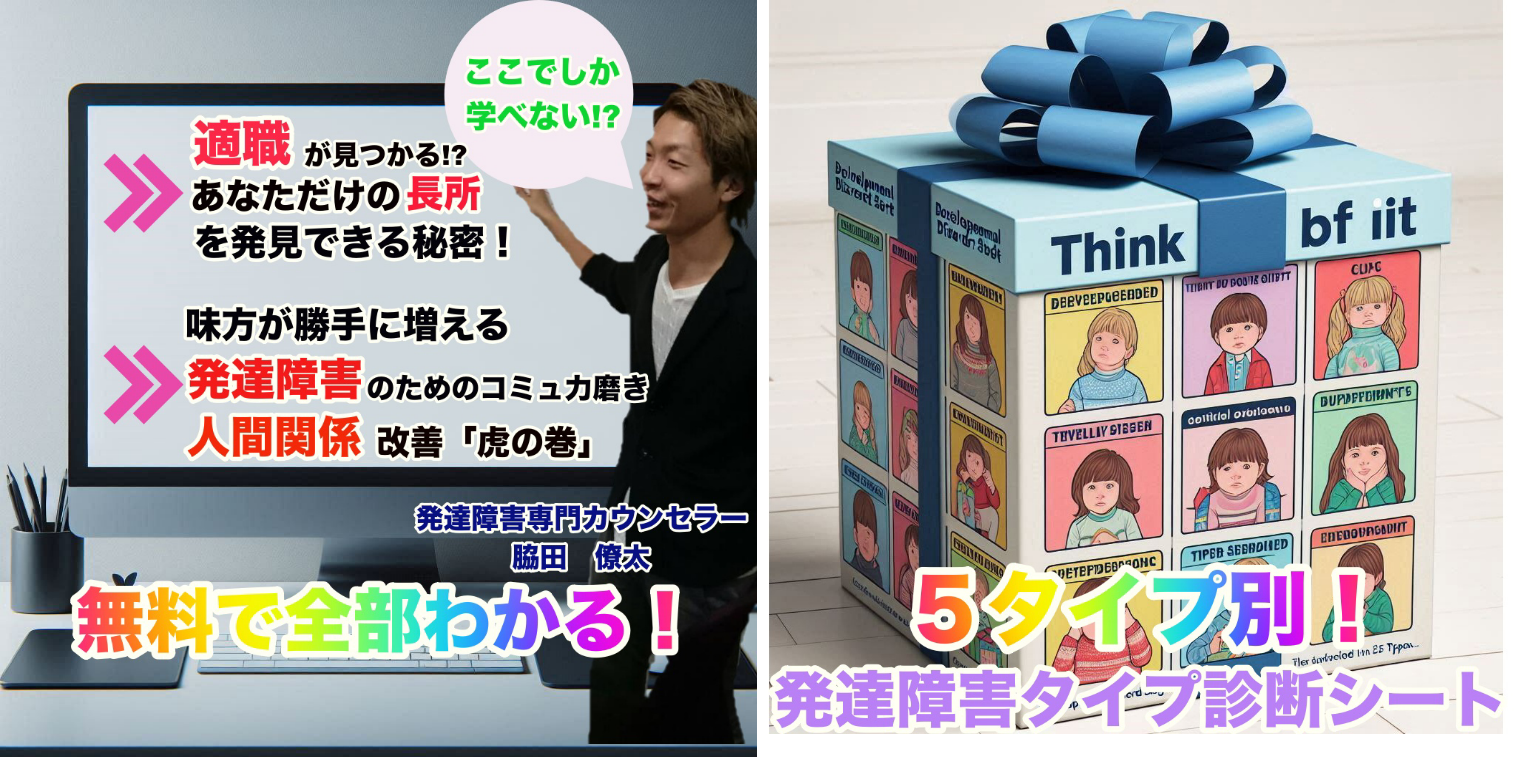 現在、友達追加特典として発達障害の中でも5タイプに分類し、自分の得意不得意がわかる
現在、友達追加特典として発達障害の中でも5タイプに分類し、自分の得意不得意がわかる